お知らせ
下水道管路内の漏水調査方法と止水工法について
見つける・止める・再発させないための現場対策
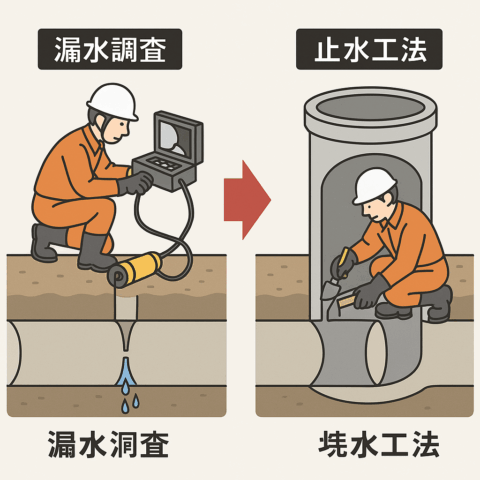
下水道管路内で発生する**漏水(地下水や雨水の流入、逆に下水の漏出)**は、目に見えないところで進行し、
・地盤沈下の原因
・マンホール浮上
・構造部の中性化促進
など、**二次的被害につながる“静かな劣化”**です。
この記事では、**「どこで漏れているかを見つける方法」と「どうやって止めるか」**を2部構成で実務的に解説します。
第1部:漏水調査の方法(発見編)
✅ 1. 目視によるTVカメラ調査(最も一般的)
高解像度TVカメラで管内を全周撮影
継手部やクラック部からの流入・にじみを確認
**逆流跡・濡れ筋・白華(エフロ)**がヒントに
📌ポイント
・晴天時の調査が基本(地下水漏水を把握しやすい)
・ズーム・自動トラッキング機能付きカメラ推奨
✅ 2. 管口カメラ・斜め撮影で細部確認
マンホールから斜め方向に照射し、継手の状態や巻立て部を確認
コンパクトなカメラで小口径管にも対応
📌使い分け
・短距離・狭所向け
・目視では判断しづらい“にじみ”にも強い
✅ 3. 染色水試験(流入経路確認用)
管外部に色水を撒き、管内へ流入するか確認
水道漏水・地上からの浸入経路を特定するのに有効
📌用途例
・雨天時に白華発生していた箇所の再調査
・周辺宅地・歩道の雨水進入調査
✅ 4. 夜間の流量観測(不明水の流入把握)
使用者のいない深夜帯の流量変化を記録
地下水や雨水の流入有無を定量的に判断できる
📌注意点
・連続記録が必要(自記流量計使用)
・天候の影響を受けない平日深夜が最適
✅ 5. 煙試験・加圧試験(気密性評価)
煙を管内に充満させ、どこから漏れるかを確認
またはエアー加圧して圧力変化で漏水有無を判断
📌実施は限定的(新設工事・接続部検査など)
第2部:止水工法の種類と選定(施工編)
✅ 1. 樹脂注入止水工法(万能型)
漏水箇所に穿孔し、ウレタン系樹脂を高圧注入して止水
浸入水に反応して膨張・硬化するタイプが主流
📌適用条件
・継手部、クラック、打継ぎ、管口部など
・マンホールやコンクリート管全般に有効
✅ 2. 外圧止水パッカー(内面から塞ぐ)
- 管内に膨張型のパッカーを設置し、薬液を圧入→固化
- TVカメラで見ながら局所的にピンポイント止水
📌利点
・施工が早く、交通規制なしで対応可
・水位がある現場でも対応しやすい
✅ 3. Vカット+止水モルタル充填(打継ぎ部・人孔向け)
漏水部を斫り(Vカット)→モルタルやエポキシで補修
📌向いている現場
・人孔構造部の打継ぎ部・巻立て部
・止水だけでなく補強効果も狙える
✅ 4. 内面ライニングによる止水(全面処理)
- 管内全周に塗布材(ポリマーセメント・樹脂)をライニング
- 微細なクラックやにじみ漏水を一括対応
📌適用条件
・漏水箇所が複数ある場合
・更生工事と併用されることも多い
✅ 5. 構造更生+止水一体型(反転工法・形成工法など)
- 全面的な更生工法で、漏水も構造もまとめて更新
- 長期耐久性・再発防止に最も優れるがコストは高め
まとめ:調査→止水の“流れ”がカギ
下水道の漏水対策は、「いかに漏れを見つけ、的確な方法で止めるか」が成否のカギ。
✔ TV調査や染色などで**“見えない漏水”を可視化し
✔ 漏水原因に合わせた止水工法を的確に選ぶ**
📌 ポイントは以下の通り:
✅ 漏水箇所は複数原因が重なっていることが多い
✅ 止水だけでなく、周囲の構造健全性確認も重要
✅ 局所止水でダメなら、面処理 or 更生を検討






