お知らせ
中性化試験の基本とは?
フェノールフタレイン法の原理と手順
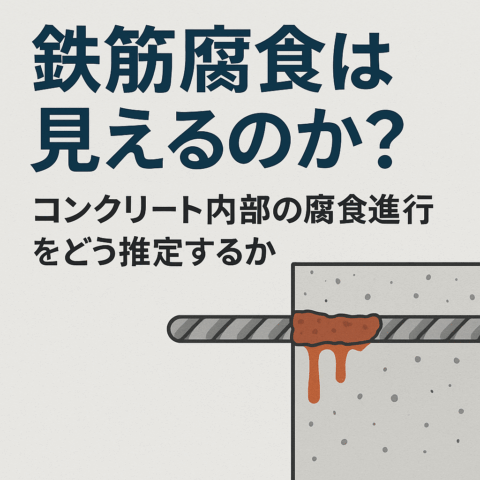
コンクリート構造物の寿命を脅かす“見えない劣化”――それが「中性化」です。
目で見ただけでは分からないこの進行を、「色の変化」で可視化する手法が、中性化試験(フェノールフタレイン法)です。
本記事では、中性化の基礎知識から、フェノールフタレイン試験の原理・準備・手順・注意点までを丁寧に解説します。
1. 中性化とは何か?なぜ問題なのか?
✅ 中性化のメカニズム
通常のコンクリートは強アルカリ性(pH12〜13)
外気中のCO₂が内部に浸透し、アルカリ分と反応
徐々にpHが低下し、鉄筋を守る“パッシブ膜”が壊れる
つまり、中性化が進行すると――
🔽 鉄筋が腐食しやすくなり、構造全体の劣化が加速するのです。
2. 中性化試験の目的とタイミング
🎯 こんなときに実施すべき!
築30年以上のRC人孔やスラブ構造物の点検時
錆汁・クラックなど“劣化兆候”が確認されたとき
更生・補修の要否を定量的に判断したいとき
中性化対策工法(表面保護など)の効果判定にも◎
3. 試験方法:フェノールフタレイン法とは?
🧪 基本原理
**フェノールフタレイン溶液(pH指示薬)**を使用
アルカリ性(pH10.5以上)→ピンク色に変化
中性化部分(pH10以下)→変色せず無色のまま
→ この“色の境界線”が、中性化の進行深さを示す!
4. 準備と使用機材
| 機材 | 用途 |
|---|---|
| フェノールフタレイン溶液(1%) | 試薬として使用(市販可) |
| スプレーボトル | 均一に噴霧するため |
| コアドリル or 斫り機 | 試験面の新鮮な断面を露出 |
| ノギス・定規 | 中性化深さの計測 |
| ワイヤーブラシ・ガーゼ | 表面清掃 |
| 保護具(手袋・ゴーグル) | 安全対策 |
5. 試験の手順(現場作業)
📋 STEP1:新鮮な断面を露出
コア採取 or コンクリート表層をチッピング
断面は平滑で清潔に保つことが重要
📋 STEP2:表面の清掃
粉塵や水分をガーゼやエアブローで除去
発色の妨げになるため丁寧に!
📋 STEP3:フェノールフタレインを噴霧
スプレーで試薬を軽く吹きかける
10〜20秒程度で色の変化が現れる
📋 STEP4:中性化深さの計測
ピンク色の変色範囲=未中性化領域
無色の部分=中性化済み領域
表面からの深さをノギスで測定して記録
6. 判定の目安と評価基準
| 中性化深さ | 判定の目安 |
|---|---|
| 0〜10mm | 健全。鉄筋かぶり内に到達していない |
| 10〜20mm | 経過観察(築年数によっては注意) |
| 20〜30mm | 要注意ゾーン。鉄筋腐食の可能性あり |
| 30mm以上 | 危険レベル。早期補修・対策が必要 |
※RC人孔の鉄筋かぶり厚さは20〜30mm程度が一般的
7. よくある誤解と注意点
| NG例 | 対策 |
|---|---|
| 古い面に試薬を吹きかける | ➤ 必ず“新鮮な断面”で判定 |
| 試薬をかけすぎて流れる | ➤ 霧吹き程度に軽く噴霧 |
| 発色の違いを主観で判断 | ➤ 写真撮影+スケール付き記録で客観性を確保 |
| 濡れた面で発色しない | ➤ 乾燥 or タオルで水分除去後に実施 |
8. 試験結果をどう活かす?
鉄筋腐食のリスク評価に活用
更生設計前の「健全性判定」
補修工法選定の根拠に(表面保護材/再かぶりなど)
調査報告書での数値データとしての信頼性確保
まとめ:色で“内部の危険”を見抜く一歩目
中性化試験は、構造物の見えない劣化を“目で見える形”に変えるシンプルかつ強力な診断手法です。
✅ フェノールフタレイン法は誰でも扱える“現場対応型の評価法”
✅ 正しく準備し、色の境界線を正確に測ることが重要
✅ 記録と併用し、設計・補修・報告へつなげるのがプロの仕事!






